今回は参加だけで発表はしませんでしたが気になったことだけ報告します。
教育講演やシンポジウム及び研究発表等があった中で「糖質制限」についての最新研究をピックアップします!
「肥満者の減量に於いてはPFCに関係なく摂取総カロリーを減らすことで達成できる」 太る原因は食後血糖値の過剰であり、カロリーではありません。
もちろんカロリー過多は、食事量の過剰になるのでその分の糖質も増えて食後血糖値も上昇し過ぎますが、血糖値を上げるのはカロリーではなく糖質(炭水化物)ですのでPFCバランスの考慮は欠かせません。
※P(Protein=タンパク質)、F(Fat=脂質)、C(Carbohydrate=炭水化物)
「糖質制限すると早期に減量できるが糖質を制限した分、脂質やタンパク質が過剰になる」
食事に占める糖質(炭水化物)はご飯などの主食で、タンパク質は肉や魚介類などの副菜ですが、脂質の割合は肉や魚に含まれたり、調理に使う油脂が殆どで脂質の食品はありません(バターやラードを食べる方は別ですが…)。
従って、糖質制限して食事量を減らさなければタンパク質は増えますが、脂質については調理法を考慮すればそれほど増えることはありませんし、タンパク質の比率は増やした方が痩せやすくなります。
その他、実証研究で糖質制限の有効性を認めているにもかかわらず色々こじつけながらカロリー制限を優位に立たせようと躍起になっていました。
極端な糖質制限はNGとか当たり前ですし、中には糖質制限のデメリットとして、「肉が増えるので食費がかさむ」と言うのがあり苦笑してしまいました。
食費がかさむ何て余計なお世話…、確かに食生活には経済的な理由も考慮しなくてはなりませんが、こんなの科学ではありません!
糖質制限食は状況によって対処法を変えなければならないのです!
糖尿病の方の食事療法はむしろ極端な糖質制限を奨めますが、通常の減量(ダイエット)はいつもの食生活を大きく変えないことを考慮しながら間食の糖質だけは制限して、特に夕食は低GI食(食後血糖値を抑える食事)にします。
医学会ではまだまだ根拠に乏しいカロリー指導が主流であり、糖質に注目した研究や指導の報告は少ない気がしますし、GI値の研究に至っては少数派です。
※永田理事のFB投稿より引用
☆ランキング参加中!バナーをクリックして頂けると幸いです。☆
にほんブログ村


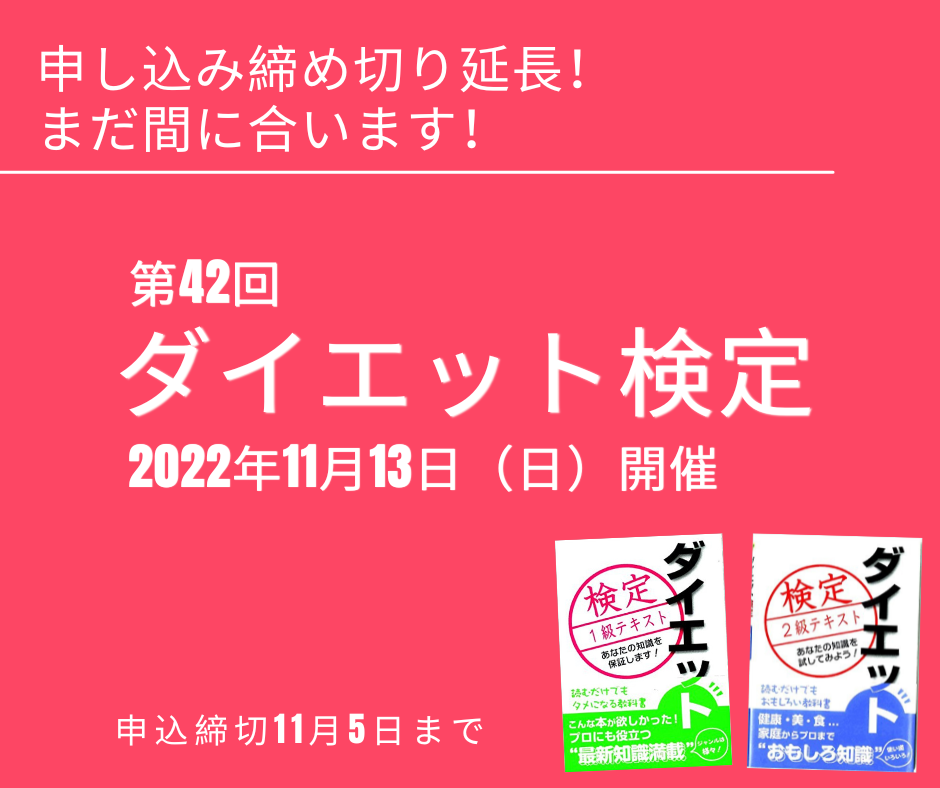

0 件のコメント:
コメントを投稿